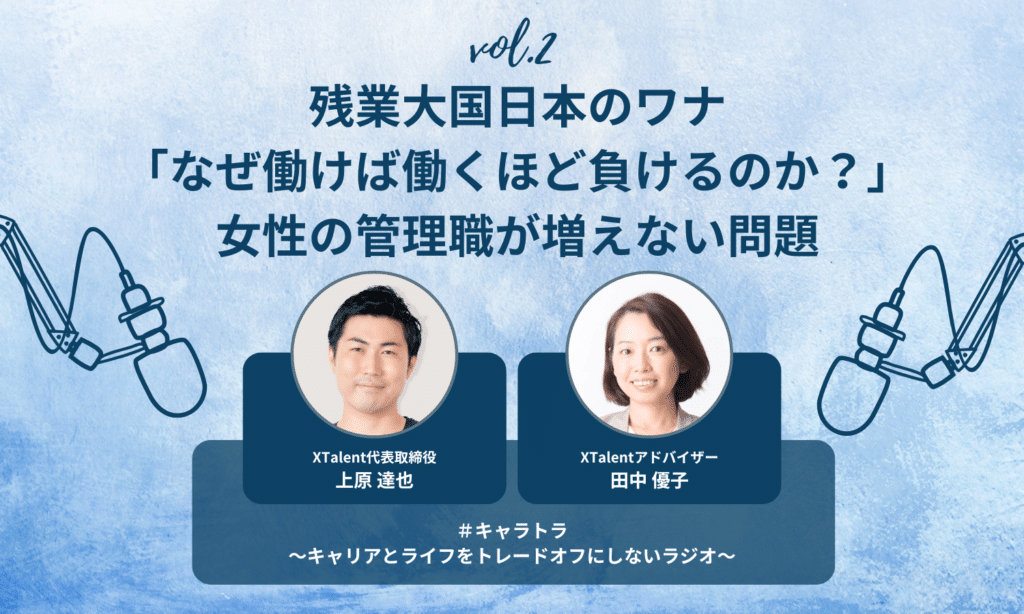(※2024年10月24日放送の「#キャラトラ」を記事化したものです。)
こんにちは!ワーキングペアレンツのための転職サービス『withwork』です。
現在進行形で企業経営に携わる、 XTalent代表・上原達也とXTalentアドバイザー・田中優子が、 男女やケア責任のありなしに関わらず、誰もが活躍できる組織運営について雑談していきます。
今回のテーマは、「長時間労働」と「女性の管理職が増えない」問題について。
ハードワークを良しとする会社は、その価値観に合致する人しか残らない
上原:
先日、『山田進太郎D&I財団』の石倉秀明さんのSNSの投稿を見たんですね。その投稿には、「労働時間を短くしなければ、女性の管理職は増えないのではないか。組織でいろんな人が意思決定層に上がっていくためには、やはり残業なしでも仕事ができる、成果を出せる社会にならないとダメなのではないか。」といった内容が書かれていました。
以前、僕と田中さんの間でも「労働時間ではなく、成果を評価することが当たり前になったらいいよね」という話をしましたよね。
田中:
性別関係なく、ハードワークを良しとする会社は、その価値観に合致する人しか残りません。そういった意味では、リスキーだなと思います。ハードワークをしたい人を集めて競争を促して成果を上げて、それで会社が成功するのであれば、1つの経営戦略の形と捉えることもできると思いますが…。ただ、その会社の女性比率は当然増えないでしょうし、会社の価値観に同意できない男性社員も増えないでしょう。「それでもいいのだ!」という会社があってもまあいいのかなとも思いますが、「そういったカルチャーで成功している会社もあるんだから、我が社もそれでいいんだ」と考えるのは、もう今の時代「違うのでは?」と思いますね。
年齢を重ねると、価値観やワークスタイル、ライフスタイルは変わっていきます。20代の頃はハードワークができても、子どもが産まれたり、介護の必要が出てきたり、自分自身が体調を崩したり…と、ライフステージの変化によって様々な事情が出てきますよね。ハードワークを良しとする会社であれば、もうその会社には残れなくなってしまいます。そういった人が辞めていく時に、会社は「新しい人を採用するから別にいいです」って言えるほど、「今、市場に人材が潤沢にいるんでしたっけ?」と思いますね。
上原:
たしかに、「ハードワークをしたい人を集めて競争を促して…」というのは、10年〜20年ぐらい前だったらできた戦い方のような気がしますね。その戦略でずっとやってきて、すでに大企業となり、採用力も高いという会社は一定数あると思います。一方で、やはりそういった会社は今、20代の離職率が高いと感じますね。とくに女性が辞めていくケースが多い。
ごく一部の、業績もすごく良くて採用ブランドもある会社だと、成長したい若手を吸収して、 どんどん入れ替えていくという戦い方が維持できるのかもしれません。しかし、規模の小さい会社が「あの会社が成功してるんだから、自分たちもできるはず!」と同じ戦略でいこうとすると難しいのではないかと思います。
先日、『ユニクロ』という、代表の柳井さんのストーリーを描いた本を最近読んだのですが、経営者のビジョンや乗り越えてきたことなど、多くの学びがある一方で、やはり働き方がハードだなとも思いました。当時は勝つためにその働き方が絶対に必要だったと思うのですが、「今はどうだろう?」と問うことが経営の感覚として大事になってきていると思います。
大きな変化を生み出すには「ルール」を変えるのも1つの手
田中:
社会全体として女性の管理職比率を増やすことへの関心は高まっているので、「ジェンダー平等を実現するために労働時間を減らす」という政治アプローチを取るのも、それはそれでアリだと思います。例えば、週休2日制。かつては、企業も学校も週休1日だったのに、今は週休2日を当然だと思っていますよね。なので、「週休3日にします!」とか、「標準労働時間を8時間じゃなくて6時間にします!」を法律上でやってしまうのは、解決策の1つだと思います。個々の会社ではなかなか意思決定できないけど、政府が旗を振るならできるということもありますよね。
上原:
法律は強いですからね。結局、すごく大きな変化ってそういうものでしかなかなか起こせないというのはありますよね。
田中:
労働や残業の規制にせよ、週休何日にせよ、女性の管理職比率にせよ、「そういうルールなんです」としてしまえば、みんなブーブー文句言いながらも、10年〜20年後には「え?そんなことが許されていた時代があったんですか?」となるくらい、常識は変わるのではないかと思います。
上原:
「女性の働き方」をテーマにロビー活動を長年やっている方とお話していても、法律でも「努力義務」だと弱くて、「義務」になった途端に大企業はすぐに動くそうです。
加えて、とくに上場企業に対して「投資家から投資を受けるためには、企業はこうあらねばならない」という視点は、日本では一部の会社にしか効いていないと感じます。人的資本経営のトレンドを見ていても、機関投資家や海外の投資家から投資を受けられる会社は限られていて、該当しない会社は十分には動いていません。
経営資源で「ヒト・モノ・カネ」とよく言いますが、個人的にはカネよりもヒトの動きの方がインパクトは大きいのではないかと思っています。ヒトの議論でいうと、20年後の日本は「20歳の人口が70万人もいない」という強烈なファクトがあるんですよ。
「長時間労働=成果を出す」ということ自体が思い込み?
田中:
企業がミッションやビジョンを実現するために投資家からお金を集めるように、「人的資本」も集めないといけないですよね。人的資本を集めるための必要な要素として「働き方」があります。人を集めて、かつ、その人たちが長くパフォーマンスを出してくれるような仕組みを作れるかどうか。人件費をただのコストだと捉えるなら、「安くていっぱい働かせる方がいい」となりますが、もうその方法では企業は成長できない、結果を出せない時代になっていると思います
そもそも「長時間労働=成果を出す」ということ自体が思い込みかもしれません。例えば、かつて製造業では工場の稼働時間が長ければ長いほどたくさん製品を作れました。しかし、機械やAIができることも増えて産業構造も変わってきている中で、「人が長時間働いた方が成果を出せる」なんて、その因果関係を疑う方が大事なのではと思います。
実際どうなんですかね?日本人の労働時間は、やはりグローバルに見ても長いのでしょうか?
上原:
長いですね。
田中:
でも、日本企業はグローバルで勝てていない。だから、「生産性が低い」と言われてるのですが、「長時間労働と成果には因果関係がない」ということになりませんか?
上原:
これは強烈なロジックですね。
企業として成長するには、世の中の変化を捉えていかなければならない
田中:
「何かを変える」というのはすごく時間がかかります。例えば、新しいAIやロボットを導入しようとすると初期投資も必要だし、使い慣れるまでは現場から文句が出たりと、コンセンサスコストがかかる。でも、導入してしまえば、長期的にはいろんなことが改善する。なのに、そういったものを取り入れる意思決定をただ避けて、20世紀の最初の頃からやってるようなことばかりして思考停止しているから、「長時間労働に価値がある」ということになってしまうような気もしています。
上原:
様々な場面で今、そういったことが起きてますよね。僕自身の体験談なのですが、昔勤めていた会社の上司がすごく議事録に厳しくて。そのおかげで議事録をまとめる力を鍛えられて、自分でも「議事録スキルは大事だな」とずっと思っていたんです。でも今は、AIに「会議の内容をまとめて」と一言指示するだけで完璧な議事録が上がってくるようになりました。自分が大事にしてきたスキルが否定されたような気がしました。そういった変化が、今各所で起きてると思います。でも、そのことに気づいてない人もたくさんいて。気づいてない中で「長時間労働が大事だ」と言ってるのは、たしかにまずいですね。
田中:
たくさん起きていると思いますよ。例えば、「漢字って書ける必要ありますか?」「電子機器に入力できればいいので、読めればそれでいいんじゃないですか?」など。私もコンサル時代たくさん議事録を書きましたが、自分の考えを整理するのに役立ったのも事実だけど、今の時代にそのスキルを磨くことにどこまでの価値があるのかというと、「どうなんだろう?」と思ったり。パワーポイントもかつては必要だったかもしれないけど、今は…。そういったものが色々とありますよね。
上原:
企業の成長やミッション、パーパスを叶えるためには、世の中の変化も捉えていかないといけませんね。テクノロジーや人口動態の変化を捉えて議論していかないと、ズレた議論になってしまうリスクがあるというのは意識したいです。
あとは今後、人材が今まで以上に鍵となるので、XTalentという会社で今、withworkという“ど真ん中の事業”を展開できているのを良い機会と捉えて、この課題解決に取り組んでいきたいです。
田中:
そうですね、withworkはまさにこの課題にダイレクトにアプローチするサービスだなと思います。
上原:
ちなみに今XTalentでは、絶賛採用中です。人材紹介コンサルタントをやりたい方、マネージャーや事業責任者をやりたい方、CEOをやりたい!なんて方も、ぜひお会いしたいと思っています。気になる方はぜひご応募いただけると嬉しいです!
【3/3(月)ウェビナー開催】女も男も、管理職はつらいよ 〜昭和100年を本気で終わらせたい人の会~
「キャリアとライフをトレードオフにしない」をコンセプトに、ワーキングペアレンツ向け転職支援サービス(withwork)を運営するXTalent株式会社には、日々「管理職」にまつわる様々な悩みや“悲痛の声”が届きます。
経営者や人事担当者からは、
「女性の管理職を増やしたくても、本人が希望しない」
「組織へのロイヤリティも高いと思っていたのに、突然退職してしまった」
「管理職を期待していたが、ライフイベントを経てキャリアが停滞してしまった」
転職を希望されwithworkの門を叩いた管理職のユーザーさまからは、
「仕事と家庭を十分に両立できていない。バリバリ働きたいけど、家族と自分も大切にしたい。(30代女性)」
「ポジションが上がるごとに業務過多となる。子どもが2人いる中で妻への負担も大きくなっている。(40代男性)」
「これ以上役職を上げるとなると、共働きで成功している例が社内にいない。(30代女性)」
「今の会社の体制だと昭和の専業主婦が当たり前の部長陣も多く、会社に来て営業も遅くまでやってなんぼの雰囲気が強い。(30代男性)」
これらの悩みは表裏一体。
行き着く問いは、
「なぜこんなに管理職はつらいのか」
ところでみなさん、2025年は「昭和100年」にあたるそうです。
働き方改革や女性活躍推進が叫ばれて久しい昨今。
価値観の多様化も進む中、まだまだ根強く残る人々の固定概念。
その変化の狭間で苦しんでいる管理職たち。
私たちにいま必要なのは
「管理職像のアップデート」
ではないでしょうか。
本イベントでは、管理職に関する現状の課題と、成功事例や失敗事例、新しい時代に即したリーダーシップのあり方、具体的な解決策などについて議論していきます。
イベント開催概要
・日時:2025年3月3日(月)12:00~13:30
・オンライン開催(Zoom)
・参加費:無料
・主催:XTalent株式会社
\お申し込みはこちら/.png)