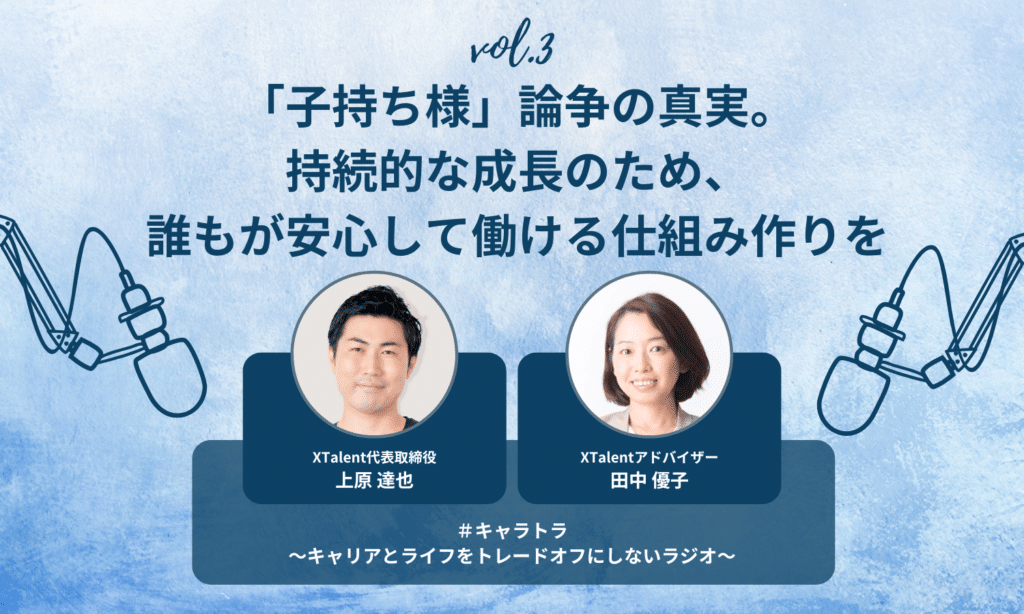(※2024年8月22日放送の「#キャラトラ」を記事化したものです。)
こんにちは!ワーキングペアレンツのための転職サービス『withwork』です。
現在進行形で企業経営に携わる、 XTalent代表・上原達也とXTalentアドバイザー・田中優子が、 男女やケア責任のありなしに関わらず、誰もが活躍できる組織運営について雑談していきます。
今回のテーマは、「子持ち様論争」について。
「子持ち様」という言葉は、どこで使われているのか?
上原:
少し前から、「子持ち様」というワードが一気にメディアに取り上げられるようになりましたよね。僕もいくつかのメディアから、「子持ち様について考えをお聞かせください」とお声がけいただきました。例えば、「子持ち様という言葉は、どのような職場から生まれるのでしょうか?」など。いろいろとお話する中で難しいと感じたのは、実際に僕自身が日常生活で「子持ち様」という言葉が使われている現場に遭遇したことがなかったことですね。
田中:
きっと面と向かっては言わない言葉ですよね。ネット上など影で言われることが多いのかなと。なので、「誰が言っているか」「どこで言っているか」が分からないですよね。
上原:
僕が過去に所属していた会社では、明らかに誰かに仕事をお願いして、その人が代わりにすごく残業しないといけないという状況や、先に帰る人が「私は子どもがいるから仕方ないでしょ」といった態度を取るような典型的なシーンを見たことはありません。自分も含め、子どもがいる人たちでフォローし合っていましたし、先に帰ったとしても、家で仕事ができる環境だったというのも大きかったかもしれません。今、withworkというワーキングペアレンツ向けの転職サービスを運営していますが、自分たちのクライアントでもそのような話は聞いたことがないですね。
どういう場所で「子持ち様」という言葉が使われるかは、もしかしたら今自分たちが身を置いているようなIT業界、すなわち比較的柔軟な働き方ができる職場ではないところで起きやすい構造なのではないかと感じています。あくまで仮説ですが。
田中:
会社が子育て中の人向けの施策のような福利厚生施策を充実させようとした時に、それに対し「逆差別だ」という人がいると聞いたことがあります。その理由としては、「子どもがいなくても、同じようなシチュエーションはありうるのだから、子どもがいる人だけにその制度があるのは不公平ではないか」といったものです。その人にとっては子育て中の方を特別視しているように見えるんでしょうね。「子持ち様」という言葉は使っていませんが、まさに子持ち様的なことですよね。そういった考えがその人の中には一部あるのだろうなと思いました。
「ワーママだからこうだろう」という無意識のラベリング
上原:
最近はあまり聞かなくなりましたが、withworkを始めた頃は、「ワーキングマザー」に関して言われることのパターンがいくつかありました。
1つはポジティブなもので、「時短勤務で働くワーキングマザーの方々は、時間が限定されている分、すごく生産性が高くて期限に対する意識も高い」といったもの。
一方で、時々あったのが、「子どもがいるからって『権利の主張』をする人がすごく多いじゃないですか」といったネガティブなもの。「すごく多い」と言われても僕はあまり納得感がなかったのですが、そういうことをおっしゃる方もいました。肌感覚ですが、どちらかというと大手出身の方にそういった傾向がありました。後者の方々にとって「権利の主張」というのが1つの共通のキーワードでしたね。
田中:
「権利の主張をする人がマジョリティか」というと、私もその感覚はありませんね。どちらかというと、申し訳ないと思っていたり、無理に頑張ろうとする人の方が多いように感じます。
上原:
「権利の主張」とおっしゃる方と話をしていると、「この人の中ではもうカテゴリーが決まっているんだな」と感じることが多かったです。本当は人によって様々なケースがありますよね。男女問わず、仕事と育児の両方を大事にしたいという方は多いですが、その中での比重は人によって異なります。「育児の時間をしっかりと確保して、仕事は少しセーブする形で臨みたい」という人もいれば、「子育ても大事だけど、仕事でも思いっきりチャレンジしたい」といったキャリア側の比重が大きい人もいらっしゃいます。でも、「ワーママ」という言葉を聞いただけで、「ワーママだからこうだろう」といったラベリングが無意識に行われてしまう。一方で、既存のイメージに引っ張られている方に、「いやいや、実態はこうなんですよ」と毎回訂正していくのも違うなと思いまして。なので、withworkを運営する中で、途中からワーママという言葉を極力使わないことにしました。
なかなか見えてこない「裏側の事情」にも意識を向けてみる
田中:
私自身、「実際に開き直って権利を振りかざす人は少ないのでは?」という感覚はあるものの、ネット上では「子持ち様」という言葉が生まれ、みんなその言葉を使う。日常生活の中でも、正面切ってではないかもしれませんが、その言葉を使い始める。そして、実際に仕事を押し付けられたり、被害を被ったりしたわけではないのに、お子さんがいて早く帰る人を「なんか楽してる」と咎める。
日本人は「同じだけ苦労しないと満足しない」と言われることがあります。「あなたはあなた」「私は私」ではない。「◯◯さんが早退しました」と聞くと、その人が早退したことによって自分が不利益を被っているわけでなかったとしても、「あの人は早退をした。ずるい」と感じる。
子育てのことに限らずですが、「子持ち様」というカジュアルな言葉が与えられたことによって、非難しても良い対象になってしまっていることが気になります。
上原:
いじめの構造にちょっと近いかもしれませんね。
ただ本当に、withworkにご登録いただいた方で、「権利を振りかざします」みたいな方には出会ったことがありません。本当にみなさん、すごく必死な状態の中で仕事や育児をこなされています。仕事が終わって帰宅したらワンオペで自分の時間がほぼない。新卒からすごく仕事を頑張ってきたのに、 子育てや介護など家庭の事情により時間の制約ができて、仕事をなかなか任されなくなった。キャリアも積んで給与もしっかりと上げてきたのに、また新卒時代並みにガクッと下がってしまった。裏側にあるもの、例えば「給料が下がった」「仕事を任されなくなった」ということも、当事者ではない人からするとなかなか見えてきません。表面上に見えるものを部分的に切り取って、「子持ち様」という見方をしてしまっているというのは、大いにあると思います。
誰もが安心して働ける仕組みをつくることが、持続的な成長につながる
田中:
一面的に物事を捉えて、実際にその人が何を抱えているかの想像がついていないというのは「子持ち様」の議論以外にも存在しているような気がします。キャッチーなので、これだけメディアも取り上げるのでしょう。ただ、上原さんもメディアでおっしゃっていましたが、例えば、実際に育休に入るとき、それを補う人が入ってくるわけではなく、今いる人でその仕事をシェアしなければいけないとなると、やはり負荷が増えてしまって「育休を取られると困る」みたいなことになります。あるいは、「育休を取りそうな人を自分のチームに入れたくない」「採用したくない」など、最近は減っているかもしれませんが、そういった問題は事実としてあるのかなと思います。
上原:
そうですね。いまの日本の労働市場を俯瞰すると、企業側は優秀な人材の確保と定着に苦心している一方で、働き手の多様なライフスタイルやキャリア観は、以前にも増して広がりを見せています。子育て中の方が早く退勤したり制度を活用したりすることは、実は“特権”というより、”より持続的に働くための工夫”に過ぎません。
もちろん、一時的に仕事の量や負荷が他の人に偏るケースもあります。しかし、そこで「子持ち様だ」とラベリングするのではなく、組織全体でカバーし合う仕組みや心理的安全性を高めるマネジメントが大切です。結果として、子どもがいようがいまいが、多様な働き手同士が互いにフォローし合える職場ほど、生産性や定着率も高くなるはずです。
働き方が柔軟に選べる企業は、今後さらに人材獲得の面でも有利になるでしょう。働き手としても、「私は子どもがいるから」と遠慮するばかりではなく、自分ができる貢献やキャリアの可能性を積極的に示していくことで、むしろ相互理解が深まります。労働人口が減少していくなかで、多様性を受け入れ、誰もが安心して働ける仕組みをつくることが、個人にとっても企業にとっても、そして社会全体にとっても持続的な成長につながるのではないでしょうか。