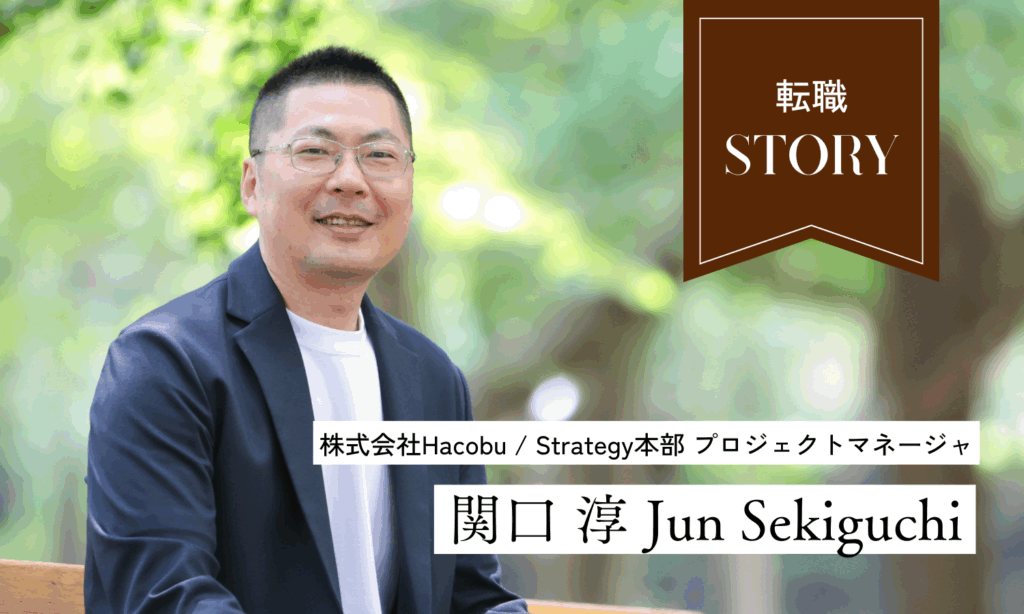今回のwithwork転職ストーリーは、「運ぶを最適化する」をミッションに、企業間物流を最適化するクラウド物流管理ソリューション「MOVO」と物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy」を展開し、データによる物流DXを支援する『株式会社Hacobu』へご転職された、関口 淳(せきぐち じゅん)さんをご紹介します。 (※2025年4月時点のインタビュー内容です)
関口 淳 / 株式会社Hacobu Strategy本部 プロジェクトマネージャ 新卒でエンジニアリングコンサルティング企業に入社し、主に建設業向けのシステム構築に携わってきました。ソリューション提案営業に従事したのち、チームリーダー、マネージャとしてシステム提案や新規ビジネス検討を担当。withworkを介して2024年10月にHacobuへ転職。ソリューション事業の立ち上げメンバーとして、基盤作り、顧客への提案、システム構築等を担当。
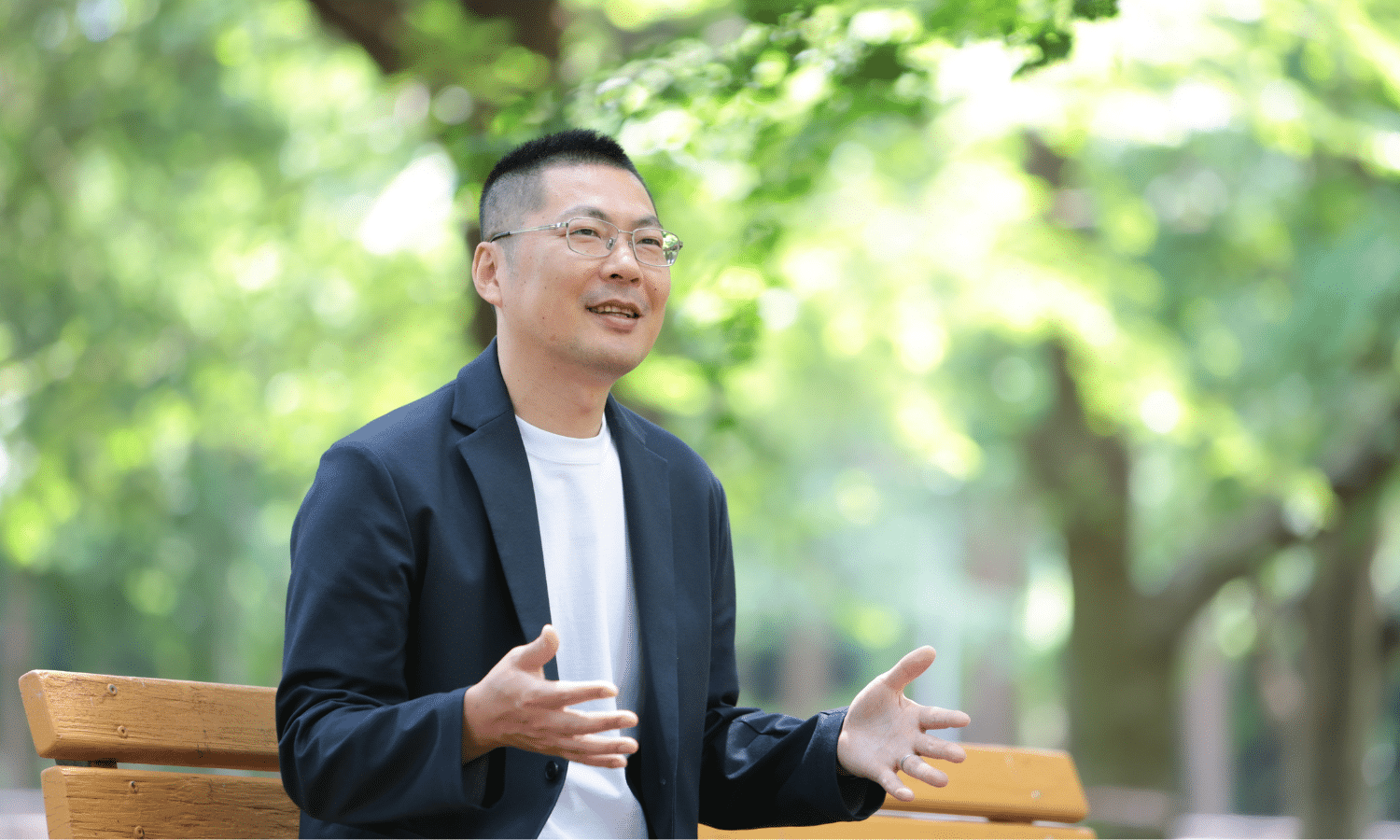
ーー転職を検討し始めたきっかけは?
前職でリーダー職、マネージャ職に就いて3年が経過した頃、自分のキャリアを改めて考え、とても怖くなったんです。
中間管理職として社内外の調整を行い、日々の業務をこなすことに精一杯。チャレンジすることは、以前に比べて少なくなりました。50歳前後になった時には、後進が育ち、自分もいつかはこの役目を終える日がくると想像したら「新たなことに取り組む意欲を維持できているのだろうか」という疑問が湧いてきました。
どんな環境でも自分次第と言えばそれまでですが、技術変化や取り巻く周囲の環境が刻々と変化する中で、5年先も10年先も同じようなことをやっている姿が想像できてしまい、このままではいけないと感じたことが1つ目のきっかけです。
また、フルタイムで働く妻と協力しながら子育てする中で、上の子が小学校に入ったらどうなるのか…という何とも言えない不安がありました。
長女は引っ込み思案な性格で、環境の変化に慣れるのに時間がかかる子でした。事情があって保育園を転園した時も、登園時にスムーズに親から離れられるようになるのに1年以上かかりました。来年は小学校に入り、学童に行くことになります。
今よりも大勢で多様なコミュニケーションが求められる場所で、馴染めなかったら…そもそも学校に行けなかったら…と考えると、不安が拭えませんでした。
我が家は両親共に高齢で実家は遠方。何かあっても常に自分たちで解決しなければなりません。前職の職場は他社に比べれば子育てに理解がある方でしたが、出社が必須ということもあり、いざという時は夫婦どちらかが会社を辞めるしかないかなぁ…と話していました。
どんな時も子どもが安心して帰ってこられる場所を、絶対に用意しておきたい。そんな気持ちを抱く中で、もう少し柔軟な働き方ができないかと考えたことが2つ目のきっかけでした。
ーーwithworkにご登録いただいた経緯は?
「柔軟な働き方」といっても、安定した職と小さい子どもがいる中でリスクを負ってまで転職する意味はあるのかな…と悩んでいたところ、SNS広告でwithworkの「キャリアもライフも諦めない」という言葉を見かけ、まさに求めていたのはこれだ!と登録したのをよく覚えています。
ーーwithworkの転職支援を受ける中で印象的だったことは?
転職先の企業を無理に勧めるのではなく、私自身の考えや希望を尊重し、真摯に話を聞いてくれたことです。
そして、それを一つずつ言語化してくれたことで、私が大切にしている想いが整理できました。その上で「本当に納得して、行きたいと思える企業に応募しましょう」とおっしゃってくれたことを覚えています。

(2024年に開催されたwithwork5周年記念感謝祭にて 担当の重松とご家族と)
ーー現職のお仕事内容を簡単に教えください。
株式会社HacobuのStrategy本部にてプロジェクトマネージャに従事しています。当社の事業「クラウド物流管理ソリューション事業」「物流DXコンサルティング事業」に次ぐ新たな柱としてソリューション事業(SaaSだけでは解決できない物流DX課題をSaaS周辺のサブシステムを構築する、もしくは、SaaSではなかなか使えない最新のテクノロジーを駆使することで解決していく事業)の立ち上げにあたり、運用フローや枠組み作りなど行う一方で、実際にお客様への提案やシステム構築を実施しています。
ーー現職への入社の最大の決め手を教えてください。
「運ぶを最適化する」そのミッション実現のためのロードマップが明確であり、CEOの太郎さんとの会話で、自分自身が「何のために働いているのか?」という不安感を払拭するのに十分な理由が見えたからです。
もうひとつ、代表自身が積極的に子育てをされていることも大きな後押しとなりました。
以前、太郎さんが「『仕事を頑張ること』はもちろん大切だけれども、『家族との時間を大事にすること』もとても大切だと思う。仕事の時間が取れないといったことは起きるかもしれないけれども、家族の時間を大切にすることは本人のモチベーションに繋がるし、回り回って仕事の生産性向上に少なからず還ってくると思っている。そういった良いループを回せるような組織でありたい。」といった発言をされていました。
「あー、この方は家族との関係を大切にされている、そこを犠牲にしたような働き方から生まれた成果だけを善しとしないんだな」と感じ、共感したことを覚えています。
ーー実際に働いてみて、入社前と現在でギャップなどはありますか?
良い意味で想像以上に、会社が掲げるVision、Mission、7Valuesが社内に根付いていました。
バックグラウンドは多種多様にも関わらず、みんなが同じ目的意識を持っているからこそ、常に建設的な会話ができ、スピード感を持って前に進められています。
例えば、Valueに「当事者意識に、火を付けよう / Spark owership」というものがあるのですが、会議でやらなければいけないタスクが発生した際、Aさんが「私、これやっておきます」、一方でBさんは「じゃあ、ここは私がまとめます」というように、自然とボールが拾われ、形作られていく光景がよく見られます。
依頼されてやるのではなく、一人一人が当事者意識を持って仕事を進めているんです。
ーーワーキングペアレンツ視点で見た時、貴社のカルチャーや風土はいかがですか?
組織として「ワークハード&ファミリーファースト」を掲げていて、かつ子育中の社員が多いので、突発的な休みや中抜けは気兼ねすることは全くありません。
役職を問わず「子どものお迎えがあるから」「学校の行事があるから」「習い事の送迎で」など仕事を抜けるタイミングがありつつも、中抜けから戻ってきたら依頼事項に対しては皆さんきっちりと対応しています。
家族との時間も大事だし、働くことも大事に思っているような感じで、まさに「ワークハード&ファミリーファースト」。それを当たり前に受け入れ、行動できているのは素晴らしいなと感じます。

ーー転職後、キャリア観や仕事に対する取り組み方に変化はありましたか?
転職前に抱いていた何のために働くのかといった漠然とした不安感はなくなり、「社会インフラである物流を維持するために自分に出来ることをする」とシンプルに考えられるようになりました。また、仕事についてもフル出社からリモートワーク主体となったため、家族の時間に影響しないよう限られた時間内でパフォーマンスを出すための段取りは、より意識するようになりました。
ーー転職後、ご家族との関係性やご自身の人生において変化はありましたか?
元々は夫婦ともにフル出社であったため協力して家事育児を行ってきました。ですが、やはり妻に負担を強いていた部分も多かったと思います。今は会社の懇親会など「気にしなくていいよ」と積極的に送り出せるようになり、誰かに負担を押し付けているといった感覚から解放されました。
何より、家族みんなで夕食を食べるという「在りたい姿」を実現できて家庭の幸福度が上がりました。家族で一緒の時間を過ごすという「今しかできないこと」を大切にする想いから、転職後は週末の家族旅行もとても増えました。これも意識の変化の結果かなと感じています。
ーーこれからのキャリアに対する展望や希望があれば、教えください。
自分が踏み出した一歩が少なからず、社会課題解決の小さな一歩だったと思えるようなキャリアを歩んでいきたいです。将来子どもたちが進路に悩んだ時、自信を持って働くことの意義を伝えられる生き方をしているか、その軸は持ち続けたいですね。
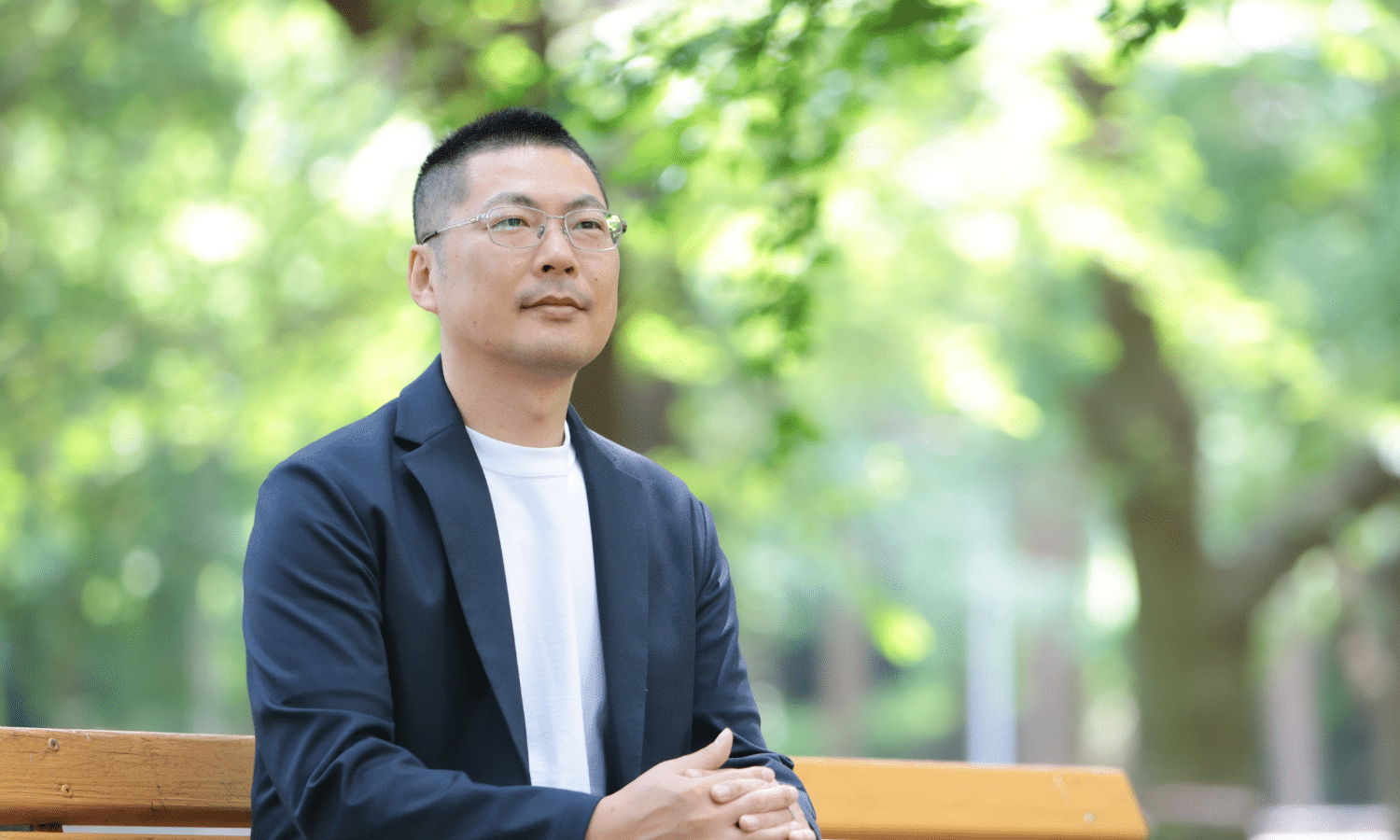
キャリアとライフをトレードオフにしたくないと思ったら、withworkにご相談を
私たちwithworkは、キャリアとライフをトレードオフにしたくないと願う皆さんへの転職支援を行っています。 働くお母さんお父さんはもちろん、これから結婚や妊娠などのライフイベントを控えている方、不妊治療中の方など、ライフを犠牲にしない働き方をめざし、自分の理想のキャリアを描いていきたいユーザーさまに、withworkは徹底的に寄り添います。
「まずは情報収集から始めたい」「同じような境遇の方の転職成功事例について知りたい」という方は、ぜひお気軽にwithworkにLINE登録&ご相談くださいね。
「キャリアもライフも在りたい姿を実現したい」
withworkはそんなビジネスパーソンの想いを全力で応援します。
撮影:Photographer Tomo