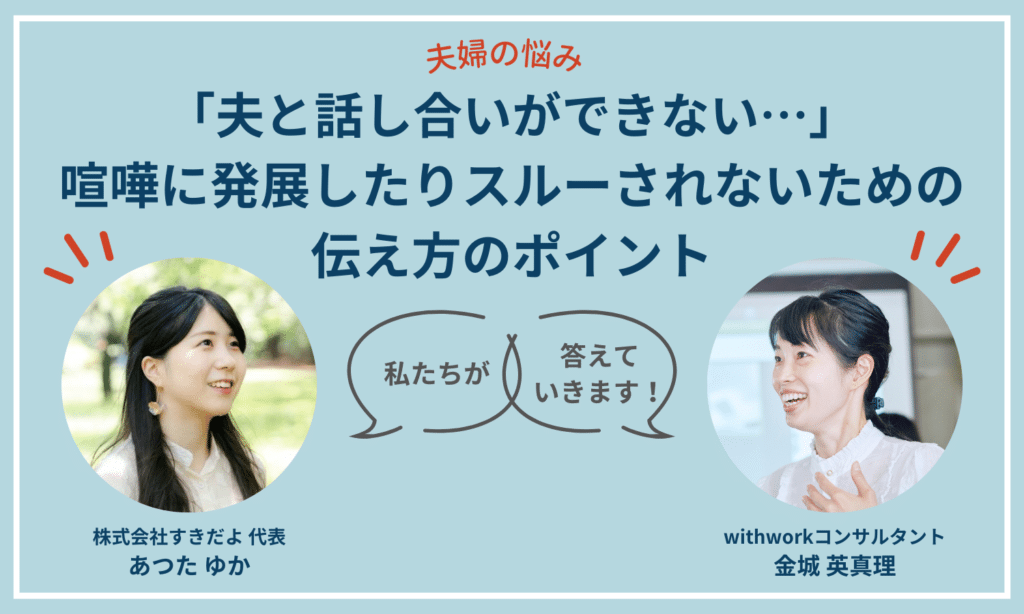こんにちは!ワーキングペアレンツのための転職サービス『withwork』です。
日々、キャラトラのリスナーさんから寄せられる、パートナーとのコミュニケーションに関する様々な悩み。
その解決のためのヒントを、『株式会社すきだよ』代表のあつたゆかさんに伺ったので、全3回にわたりお届けしていきます!
・前編:3分に1組が離婚?!夫婦間の関係悪化を予防するアプリ「ふたり会議」に込められた想い
・中編:悩み相談①「妻の機嫌が悪い」「スキンシップを拒否される」
・後編:悩み相談②「夫と話し合おうとしても取り合ってくれない」→★本記事
<スピーカープロフィール>
悩み相談「夫と話し合いができない時、どうすればいい?」
金城:
今回は、「夫婦間の話し合いが上手くいかない時はどうすべきか」というテーマで、あつたさんにお話を伺っていきたいと思います。
あつた:
改めまして、カップルテックのスタートアップを運営しております、『株式会社すきだよ』代表のあつたゆかと申します。よろしくお願いします。
金城:
今回もキャラトラのリスナーさんからお悩みをいただいています。 男性のパートナーがいる女性側のお悩みです。「夫と話し合おうとしても取り合ってくれず、家事や子どもの教育に関することを相談したくてもできない。 仕事が忙しくて疲れているのはわかるけど、家にいても何もしてくれなくて不満がたまる一方。」というお悩みです。
あつた:
withworkさんでもよく聞くお悩みですか?
金城:
よく聞きますね。中編では、あつたさんから「パートナーとのコミュニケーションがすごく大事」というアドバイスをいただきましたが、今回は「コミュニケーションを取ろうとしても取れない」というお悩みですね。
あつた:
「取り合ってくれない」という状況にも、「完全に無視されてる」「生返事で済まされる」、あるいは「興味がない態度である」など、いくつかのパターンが考えられますよね。なので、今回のリスナーさんの置かれている状況によっても変わってきそうだなと思います。
金城:
たしかに状況によっていろいろなケースがありそうですね。
これは私の家庭の話ですが、うちの夫は性格的に、自分の価値観や判断基準をしっかりと持っている人で、私に限らず人の意見を聞くよりも、「自分が正しい」と思ったことを遂行することが多いんです。なので、今回いただいたお悩みは共感する部分が多いなと思って聞いていました。
あつた:
金城さんのご家庭でも似たようなシチュエーションがあるんですね。実は、この話題はwithworkさんとの事前の打ち合わせの中でも、とても盛り上がったテーマなんです。それだけ多くの方が悩んでいるテーマだと思いますので「夫婦で話し合いをできるようにするにはどうしたらいいのか」というお悩みについて一緒に考えていきましょう。
いきなりアジェンダに入らない。スモールスタートな会話を意識する
あつた:
まず、よくやってしまいがちなのが話し合いの内容選びによる失敗です。
例えば、「子どもの教育」や「転職の相談」など、生活や人生に関わる大きな内容をいきなり切り出そうとして、「取り合ってくれなかった」「うまくいかなかった」とおっしゃる方が多いです。
そういった場合は、内容を小さくしてスモールスタートを意識してみるとうまくいくことがあります。話し合いというと、家事や子どもの教育など、それぞれのアジェンダがあって、テーブルで顔を突き合わせて議論するものというイメージがを持っている方が多いと思います。
でも、実際にそのイメージで話し合いを始めようと思うとハードルが高いじゃないですか。とくに普段からコミュニケーションが取れていない夫婦が時間をとって顔を突き合わせてじっくり話し合うというのはなかなか難しいと思います。なので、まずは「話し合いのハードルを下げる」ことをおすすめします。
例えば、今回お悩みをくださった方の場合、「夫が仕事が忙しくて疲れている」とのことだったので、「今日はどうだった?」と夕食時に軽く話してみたり、LINEで間接的に聞いてみたり。まずはそういった小さい話題から始めてみると良いですね。
「今日はどうだった?」という問い掛けに対して、「仕事で疲れたんだよね」など、パートナーから何かしら返事があったら、聞ける範囲で良いので「今はどんな仕事(プロジェクト)をやっているの?」とか「具体的にどういうところが大変で、疲れを感じているの?」といった具合に、相手の話を深掘りしてみましょう。
そうすることで、「具体的には今こういう仕事で責任者を任されていて、いろんな部署でセッションしなきゃいけないけれど、とくにこの部署の人が考えの硬い人で困っている」といったように、自然と相手の状況や今感じていることなどを聞き出せると思います。相手のことが分かると、「たしかにそれは疲れるよね」と自分の中でも納得できることが増えると思うんですね。
また、「 今日はどうだった?」という会話から、相手も「そっちはどうだった?」と聞き返してくれることもあるかもしれません。その時に自分の状況を少しずつ共有できると良いと思います。「私は〇〇だったよ。仕事はこんな状況で、具体的には〇〇な感じ。あとは、家庭のことだと子どもの教育について悩んでるんだよね。保育園から〇〇って話があって、相談したいなと思ってたんだ。」といった感じです。
いきなりアジェンダから始めようとせず、「今日はどうだった?」といった軽めの話題を切り口にすることで、相手も構えずに話しやすくなります。そして、少しずつ話題のハードルを上げていくイメージです。
金城:
冷静に考えると当たり前のことですけど、つい本題から入ってしまいがちで、スモールスタートを意識できていない方が多そうですね。
あつた:
多いと思います。「話し合いってどうやって始めたら良いですか?」というご相談もたくさんいただくのですが、例えば、私からすると「今日は映画を見た」という話題でも話し合いがスタートできると思っています。
「どんな映画が好き?」と質問をして、「こういう映画が好き」という回答があった時に、「どうしてその映画が好きなの?」「それっていつ見たの?」と話題を広げていくことで、相手の背景や価値観を深堀りすることができます。
話を続けていくと、「映画を見ていて将来の夢ができて今の仕事についたんだよね」といったような話になったりするかもしれません。そうしたら、「そうなんだ!そういえばこの前子どもがテレビを見ていて将来〇〇になりたいって言ってたんだよね。〇〇になるんだったら、どういう進路になるのかな」と、子どもの進路についての相談が自然とできるかもしれません。
同じように、「好きな動物」や「苦手な食べ物」など、人によってはどうでもいいと思えるような話題でも、「なぜそれが好きなのか」や「なぜ苦手なのか」と、話題を掘り下げてていく意識が、相手の考えや感情を理解するヒントになったり、話し合いのきっかけになったりすることがあります。
一見遠回りのように感じるかもしれませんが、こういった小さな話題からスタートすることが話し合いをスムーズに進めるためにはとても重要なんです。
『デュアルキャリア・カップル』という本では、「多くの夫婦は、家事や子どもの教育といった表面的な話し合いには積極的でも、その裏側にある価値観についてはほとんど触れようとしない」といった内容が書かれています。
子どもの教育や家事など、 共働きだからこそ日々直面する課題はたくさんありますよね。でも、その課題の裏側にはいろんな背景があるはずなんです。
例えば、子どもの教育についてであれば、
「私は子どもの頃にこういう教育をされていて、〇〇なところが嫌だったけど、〇〇な部分は良いなと感じていた。だから将来、子どもにこういう教育をさせたいと考えていた」→「実際に子育てをしていく中で、保育園の先生やママ友の意見を聞いているうちに〇〇と思うようになった」→「そして今はこうゆう考えをもっている」といったように、今の考えに至るまでにはたくさんの背景があったと思います。
なので、パートナーと自分自身が「どんな価値観を持っているのか」「人生で何が重要か」「今後は何を重要にしていきたいと思っているのか」など、内面の部分を毎日少しずつでも良いのでシェアしてくことはとても大切なことなんです。
そういった小さな会話のコミュニケーションを飛ばして、いきなり「子どもの教育についてAとB、どちらが良いか決めましょう」と言われても、話し合いに慣れていない夫婦にとっては「負担が大きい…」と感じてしまうんじゃないでしょうか。
結果的に、話し合いに前向きになれなかったり、話はしたものの結論に至らず疲れてしまったりして、次第に話し合い自体に苦手意識を持ってしまうのではないかと思います。
1日5分でも、お互いの考えをシェアする時間を持とう
金城:
あつたさんの話を聞きながら自分のことを振り返ってみたんですけど、子どもが生まれる前はお互いのことをよく話していましたが、子どもが生まれてからは「幼稚園でこんなことあった」など、子どもの話題が中心になっていて、当たり前のように夫自身のことを聞かなくなったなと思いました。
あつた:
そうですね。でも、子どもがいてもお互いに変化はあるじゃないですか。「子どもが生まれて優先順位が変化した」とか「仕事も前はバリバリやるのが楽しいと思っていたけど、考えが変わった」など。
家庭に関しても、「こういう風に時間を使いたい」とか「部屋を綺麗にしたいと思うようになった」「食事にも気をつけるようになった」など、大なり小なり絶対変化があるはずなんです。
なので、そういった変化やお互いの考えを軽くでも良いので普段からシェアしておくと、「私たちの家庭運営はこういう方向性がいいかもね」とか「キャリアは、元々こういう路線で考えていたけど、こっちの路線も今の暮らし方的にはありかもね」という風に、暮らしもキャリアも 子育てに対しても、「今の私たちにとってのベストはなんだろう?」という話し合いがよりスムーズにできると思います。
金城:
うちもそうですけど、「お互いの考えをシェアする」ということを意識的にしないといけない方も多いんだろうなと思いました。意識せずに過ごしてたら、どうしても子どもの話が中心になって話が進んでいってしまうので、子どもが寝た後に5分でも良いから夫と話をする時間を持ってみるとか。
夫婦が2人で話せる時間って子どもが寝ている時間が一番調整しやすいのかなと思うんですけど、子どもが寝た後はお互い自分の好きなこと始めちゃう雰囲気もあると思うので、意識して時間を作ることも大切なのかなと思いました。
あつた:
そういった時間を設けておかないと、例えばパートナーが急に「子どものことを考えて転職しようと思ってるんだよね」 と言い出して、「え?そんなこと考えてたなんて全然知らなかった…」となってもおかしくないですよね。
言った側はその決断に至るまでにいろいろ背景があったのかもしれませんが、言われた側は「でも、前に話した時はキャリアはバリバリいく予定って言ってたじゃない?私もその想定でいたから、そんなこと急に言われても困るよ…」という状況になる場合もあると思います。
仕事の話に限らず、子どもの教育とか休日の過ごし方とか、日々考え方って変わりますよね。「前はこう思っていたけど、今はこう思ってる」「前は〇〇に反対だったんだけど、今は〇〇って思う人の気持ちもわかるようになってきた」など、そういった日々の変化を夫婦で気軽にシェアできると良いですね。
シェアを習慣化することで、家事の相談や子どもの教育など、ちょっとかしこまって話す必要がある重要な話題でも、自然と話せるようになってくると思います。
自己理解がコミュニケーションの土台をつくる
あつた:
中編でもお話ししたように、「関係性の土台づくり」も大切です。
例えば、家に帰ってきても「おかえり」「ただいま」と挨拶もしないとか、パートナーが何かをやってくれたのに「ありがとう」「ごめんね」も言わない。そういう人に「話し合いをしよう」って言われても嫌じゃないですか。
なので、小さいことかもしれないですが、日々の挨拶だったり感謝や謝罪を当たり前に言い合える関係性をつくることが、お互いをケアすることにつながったり良い関係を築いていく上ではすごく大事です。
金城:
挨拶や感謝をパートナー側がしてくれない場合には、どう対応したらいいですか?
あつた:
挨拶は、もしかしたら家庭ごとに「する派・しない派」というのがあるかもしれませんが、「感謝の言葉がない」または「あまり言ってもらえない」という悩みの場合には、そのことをパートナーに話した方が良いですね。
「昔は、ありがとうと言ってたけど最近減っている」なのか「もともと、ありがとうと言わない人だと認識していて、その上で結婚した」という話なのか。場合によって、相手への感じ方や伝え方は変わると思いますが、いずれにしてもパートナーに自分の気持ちを伝えてみましょう。
「あなたが最近ありがとうをあまり言わないことが気になっている」と自分の気持ちを伝えてみます。そのうえで、例えば子どもがいる場合には、「子どもにありがとうを言いなさいと教育しているのに、夫婦間でありがとうを言っていないことについてどう思う?」とか「私はありがとうを言い合える夫婦の方が良いと思うし、感謝の言葉のある家庭で子どもを育てたいと思っているんだけど、あなたはどう思う?」といったような感じで聞いてみます。
そうすると、「え?そんなにありがとうって言えてなかった?言ってるつもりだったけど…。忙しくて気づかなかった、ごめんね」というパターンや、「あまりありがとうを言わない家庭で育ったから、それが普通だった。でも、たしかに子どものことを考えるともっと言った方が良いよね」というパターンなど、パートナー側の背景を理解することにもつながるかもしれません。なので、抱え込まずに自分の気持を素直に伝えてみることが大切だと思います。
金城:
やっぱり前提として自己理解が必要なんですね。自分は何に対して「嫌だ」という感情を抱くのか、など。
あつた:
そうなんです。ありがとうを言ってもらえないことに関しても「言ってもらえないのが嫌」で完結させずに、「ありがとうを言ってもらえない→〇〇だから嫌だ」といったように分析してみると良いですね。
例えば、「私のことを軽んじてるように感じるから嫌だ」「子どもの教育に良くないから嫌だ」「私は人に感謝の気持ちを伝えることをとても大事にしてるから嫌だ」など。
金城:
自分自身をちゃんと深掘りした上で、相手とのコミュニケーションの土台をつくっていくことが重要なんですね。
聞き方や伝え方を工夫して、相手の背景を理解する
あつた:
先ほども触れましたが、相手の背景をきちんと聞くことも大事にしてほしいです。「話に取り合ってくれないなんて悪だ!」と、自分の感情や視点で決めつけないで、「あなたと話し合いをしたいけど、できていない状態が続いているよね。それってどういった背景があるの?」と聞いてみると、案外すんなりと解決の糸口が見つかるかもしれません。
例えば、「今仕事が忙しくてすごく疲れている」という回答をもらったら、さらに掘り下げて理由を聞いてみましょう。すると、「残業が続いていて、しかも責任者になっちゃってさ」といったように、相手の状況が分かったり、話し合いの時間が取れない理由を知ることができるかもしれません。
先ほどの「ありがとう問題」と一緒で、「ありがとうを言わない」という表面だけを見ると、すごく相手が悪い人に見えるかもしれませんが、背景を深堀りしてみると「ありがとう」をあまり言わない家庭で育ったのかもしれないし、最近本当に忙しくて「ありがとう」を忘れちゃうくらいに疲れているのかもしれないですよね。
なので、最初から相手のことを決めつけて諦めたり怒ったりせずに、「私はこういう家庭を築きたいと思っているけど、今お互いの間に若干のギャップがあると感じてて、改善したいと思っているよ」とフラットな気持ちで伝えられるといいですね。
金城:
あつたさんのように、聞き方もポイントですね。
あつた:
「あなたのことを理解したい」とか「意見が聞きたい」という思いが伝わるような質問ができるといいですね。
例えば、「私は最近、あなたからの『ありがとう』が減ったなと感じていたんだけど、そんなに仕事が大変だったとは知らなくてごめんね。」「あなたの状況ももっと知りたいし、できれば『ありがとう』を言い合える家族になりたいから、改善するにはどうしたらいいのか話し合いたいんだけどどうかな?」といった感じで。
どのような話題であっても、「良い関係を築きたい」という根底は一緒だと思うんです。「これから先も、あなたと仲良く一緒に生きていきたい」という前提があるからこそ話し合いをしたいと思うのではないでしょうか。
話し合いの目的は一方的に意見を言うことではなくて、お互いの考えや意見をシェアすることだと思うので、いきなり本題を話してうまくいかないから終わりではなく、どうしたら話し合いができるか考えられると良いですよね。
相手の背景を理解したうえで、大きいボール(=話題)を打ち返すのは難しそうだから、本題にいく前に、小さいボールを投げてみる。それで相手が返してくれたらそれを1つずつ積み重ねていく。そのようなイメージで話を始めると、自然と話し合いができるようになるのではないでしょうか。
金城:
たしかにそういうふうに聞かれたら、ちゃんと話し合おうって思いますね。
相手を労る言葉や共感の言葉を添える
あつた:
「話し合いに応じてくれない」というご相談をよくいただきますが、深掘りしてみると話し合いができない理由は思っているよりも単純なことが多かったりするんです。 「そもそもタイミングが悪い」とかですね。
ちょっと極端な例と思うかもしれませんが、朝8時のもうすぐ出かけなきゃいけないバタバタしている時に「忙しいから」と言われたことで「話し合いに応じてくれない」と感じている方もいます。
あとは、「家事分担のこと早くちゃんと決めてよ!」といったように投げつけるような言い方をしてしまうと、相手も「うるさい!」と、売り言葉に買い言葉みたいになりますよね。感情が先行してしまっているだけなのに、話し合いができないと捉えている方もいます。
でも、落ち着いて考えてみたら、そもそも話し合いは相手も話しやすい環境にしないとうまくできないと思いませんか?
適切なタイミングを意識したうえで、「相手の今のコンディションはどうだろう?」と、相手への思いやりを持ちたいですよね。
例えば、私だったら仕事ですごく疲れて帰ってきた時に、夫からおかえりも言われずに、「お金と家事と子どものことと…10個のアジェンダを2時間かけて話し合おう」と言われたら、すごく嫌だなと思います。
先ほども話しましたが、「〇〇が嫌だ」と思う背景にはいろいろな理由があります。だから、話をするタイミングや伝え方は適切かどうかを確認するためにも軽めの質問からスタートすることが大切だと思います。
あとは、相手を労る言葉や共感する言葉も添えられるといいですね。「忙しいのはわかってるから、15分だけで時間もらえないかな」と言われるのと、いきなり「家事分担のこと早く決めてよ」と言われるのでは、全然印象が違うじゃないですか。
冷静に考えてみると、自分が話したい時に一方的に言葉を投げつけることを話し合いとは言わないと思います。
金城:
耳が痛いです…。
あつた:
「今すぐ話したい!」という時もあると思います。その気持ちはすごく分かるのですが、「今は相手が話しやすいタイミングかな?」「相手が答えやすくなるには、どう伝えたらいいんだろう?」と、まずは一度冷静になって考えてみてください。
金城:
話し合いをしたい時って、「頭の中でゴングが鳴って、ファイティングポーズ」みたいな雰囲気になっちゃいますよね。でも、「タイミング」「伝え方」「相手のコンディション」の3つをそろえた上でスタートするだけでも、「話し合いができない」というお悩みが解決するかもしれませんね。
あとは日常会話とか軽めの話題から入る「スモールスタート」も意識したいですね。
あつた:
逆の立場を想像すると、嫌ですよね。生理で体調がものすごく悪かったり、夜泣き対応で睡眠不足の時に、バババババって一方的に言葉を投げつけられても、「 はあ…」ってなっちゃいますよね。それなのに、相手から「話し合いをする気がない」と決めつけれてしまったら辛い…。
金城:
たしかに…!
あつた:
仕事に置き換えてみるとわかりやすいと思うのですが、会議をする時もちゃんと時間を取るじゃないですか。「◯月◯日の△時からの1時間お願いします」といった風に。とくに重要な事項を決める会議の場合は、事前に予定やアジェンダを相手に知らせますよね。
でも、夫婦間だと頭に相談したいことが浮かんだ瞬間に、相手の状況も考えずいきなり会議が始めてしまう。そんな状況が少なくないと思います。
「今日の夕食どうする?」「映画館で何みる?」など、軽い話題や相談なら別に良いと思います。でも、「子どもの進路」や「転職」など、人生や日々の生活関わる大切な相談は、しっかりと相手の状況をみながら時間を取って話し合いをした方が、お互いに納得のいく答えを導き出せるのではないでしょうか。
さらに、仕事の場合は相手に対し丁寧な話し方をしますよね。「〇〇部署で、〇〇プロジェクトというものがありまして、今回ご相談したい内容は次の3点です」といったように、聞き手に伝わることを意識した話し方や言葉の選び方をしているはずなんです。
話し方に関しても夫婦間になると、急に「なんでやってないの!!」といったように、思ったことをそのままストレートに言ってしまう。
もちろん、仕事と家族では距離感の違いがあって当然だと思います。でも、家族とはいえ個々の人間であることは忘れてはいけないと思います。仕事でも家庭でも、相手を敬う気持ちを持てると良いですね。
金城:
私は耳の痛いお話ばかりで…。反省しつつ、参考にさせていただきたいと思います。すごくためになるお話だったので、相談者さんをはじめ、「話し合いがうまくできない…」と悩まれているみなさんにとっても、いろいろと気づきがあったのではないかと思います。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。
あつたさん、ありがとうございました!
・前編:3分に1組が離婚?!夫婦間の関係悪化を予防するアプリ「ふたり会議」に込められた想い
・中編:悩み相談①「妻の機嫌が悪い」「スキンシップを拒否される」